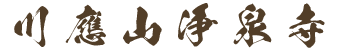仏事のいろは
Q.お焼香の正しい作法は?
①仏前に進み、一度お辞儀をします。②お香をつまみ、一度だけ香炉に入れます。③合掌し、お念仏を称えます。④一歩下がり、お辞儀をします。
※浄土真宗ではおでこにお香を押し頂くことはしません。
Q.お布施をする場合「御仏前」「御霊前」「御布施」「御回向料」など、色々ながあるけど、どれが正しいの?
「御仏前」や「御布施」と記入していただくのが望ましいです。浄土真宗では「諸法無我」という教えにより「霊」という考え方はありません。また「回向」というのは、善行の功徳を故人に送ることですが、聖者にしかできない行いです。たとえ僧侶であったとしても「自分は煩悩にまみれた凡夫である」という自覚の元に生活を送っています。
Q.納骨はいつしたらいい?
特別に事情がない場合には四十九日までに納骨します。
Q.お位牌を使う?
浄土真宗では位牌を用いません。そもそも位牌は、中国の儒家で用いられていたもので、そこに神霊が宿ると信じられていました。やがて日本の先祖崇拝と結びつき、仏教にも転用されたのですが、仏教では諸法無我の教えにより「霊」という考え方はしません。
浄土真宗では過去帳を用います。過去帳とは、先祖の記録帳のようなもので、亡き人の法名、俗名、死亡年月日などを記しておきます。

仏様の教え
仏教のいろは

Q:「仏教」ってなあに?
A:今からおよそ2500年前に生まれ、お悟りを開いたお釈迦様が、人生の苦しみの原因とその解決方法を説いた教えです。
Q:「仏教」という言葉の意味は?
A:今までに三通りの考え方がありました。
①「仏の教え」 ②「仏という真実の教え」 ③「仏になる教え」
①は「仏様が説く教え」、②は「仏様がそのまま教え」、③は「私が仏になる教え」という意味です。
さぁどれが正解でしょうか?と、聞きたくなるところですが、実はどれも間違いではありません。しかしその中でも③「仏になる教え」という考え方は他の宗教にはない仏教だけの特徴的な考え方です。キリスト教やイスラム教では「私が神になる」という考え方は絶対にしませんよね?
つまり仏教を聞くというのは、知識的に何かを理解するとか、知識を何かの役に立てようということが目的なのではなく、私自身が苦しみと向き合い、仏になっていくということが目的なのです。
Q:そもそも「仏様」ってなあに?
A:もともとの言葉は「目覚める」という言葉に由来し、「真理に目覚めたもの」という意味です。自分を目覚めさせ、他者も目覚めさせ、自分も他者も苦しみから解放する。そのような存在を「仏様」といいます。仏様は自分と他者を分けません。「あなたの苦しみは私の苦しみである」と、私たちの苦しみを自分の苦しみとして共感し「あなたを救わずにはおれない」という慈悲の心を持っておられます。
童謡詩人 金子みすゞさんの詩に「さびしいとき」という題の詩があります。
「さびしいとき」
私がさびしいときに よその人は知らないの
私がさびしいときに お友だちは笑うの
私がさびしいときに お母さんはやさしいの
私がさびしいときに 仏さまはさびしいの (金子みすゞ)
ここには「私」が寂しいときに私に対する他者の関わりが書かれています。
全くの他人であるよその人は気持ちをわかってくれません。お友達は私を励まそうと笑いかけてくれますが、本当の気持ちはなかなか理解ができません。お母さんは私の気持ちを察して、優しく接してくれます。しかしお母さんと言っても私とは異なる一人の人間。本当の気持ちを完全に理解することはできません。仏様は私の心と全く同じ心になり「あなたのさびしさは私のさびしさ」と本当の意味で気持ちを共有し、私の丸ごと全部を受け止めてくださいます。
あなたの苦しみは私の苦しみであり、あなたの喜びは私の喜びである、といつも共に同じ立場に立って慈悲の眼差しをもってはたらきかけてくださるお方を仏様といいます。
・コラム…魚は常に目覚めている??
多くの宗派では法要で「木魚」が使われています。昔、魚は目を閉じることがないから、常に目が覚めていると考えられていました。そのため、魚の形を木に刻んだ木魚を「ぽくぽく…」と叩き「魚のように常に目覚めて、精進せよ」という想いから、今でも多くの宗派で用いられています。※浄土真宗では用いません。
Q:苦しみの原因ってなあに?
A:お釈迦様は「煩悩」が苦しみの根本的な原因であるとおっしゃいました。
煩悩とは、簡単にいうと「思い通りにならない現実に対して、思い通りにしたいと思う心」のことです。例えば、あなたが「お酒を飲みたい」と思ったとしましょう。その時にあなたがお医者さんにお酒を止められていたならば「お酒を飲みたい」と強く思えば思うほど、飲めない現実に対して大きな苦しみを感じることになります。ここで大事なのは「お酒が飲めないから苦しい」のではなく「お酒を飲みたいと思う心があるから苦しい」と考えることです。仏教では苦しみの原因は周りの環境ではなく、自分の心にあると考えます。お釈迦様は、代表的な苦しみとして「生老病死(しょうろうびょうし)」という人間が生きる上で避けることのできない4つの苦しみを挙げています。「生」は生まれる苦しみ、「老」は老いる苦しみ、「病」は病気になる苦しみ、「死」は必ず命を終えていかねばならない苦しみのことです。しかし「生老病死」それ自体はもともと苦しみではなく「いつまでも若くいたい」「いつまでも健康でいたい」「いつまでも長く生きていたい」という私の「思い通りにしたいと思う心」があるからこそ先の「生老病死」を苦しみに感じてしまうということになります。
・コラム…「四苦八苦」は仏教の言葉?
「四苦八苦」という言葉を聞いたことがあると思います。実はこれ、仏教の言葉なのです。
生・老・病・死という人生の代表的な苦しみを四苦と、愛別離苦(あいべつりく・愛する者と別れる苦しみ)・怨憎会苦(おんぞうえく・恨み憎む者と合う苦しみ)・求不得苦(ぐふとっく・求めても得られない苦しみ)・五蘊盛苦(ごうんじょうく・心身を持った人間が味わう苦しみ)の四苦を合わせて四苦八苦といいます。
Q:お釈迦様の代表的な教えは?
A:お釈迦様がお悟りを開いて最初に行ったとされる説法は「四諦八正道(したいはっしょうどう)」という教えです。簡単にいいますと「4つの真理と8つの正しい実践」のことです。
四諦八正道
①苦諦(くたい) …私たちが生きる迷いの世界は苦しみに満ちているということ。
②集諦(じったい)…その苦しみの原因は私たちの「思い通りにしたい」と執着する心であるということ。
③滅諦(めったい)…苦しみが滅した安楽の境地(涅槃)こそが仏道の究極の目標であるということ。
④道諦(どうたい)…その涅槃の境地に至るために、八正道という正しい実践があるということ。
この四諦八正道はお医者さんの病人に対する接し方として例えられます。
お医者さんは病人に対して「今日はどうされましたか?」と尋ね、苦しみの状態を診察します(①苦諦)。「なるほど、これは風邪ですね」と苦しみの原因を突き止めます(②集諦)。「しばらく薬を飲んで安静にしていればすぐに喉の痛みもなくなり、熱も引くでしょう」と理想的な健康体を示します(③滅諦)。「あなたの症状に効くお薬を出しておきますね」と具体的な解決方法を示します(④道諦)。
④道諦の内容である八正道については、説明が長くなってしまいますので割愛させていただきますが、各宗派によってお悟りへの実践方法はそれぞれ異なります。
私たち浄土真宗においては「南無阿弥陀仏」のお名号こそが涅槃の境地に至るための正しい道、ということになります。親鸞聖人は「本願醍醐(だいご)の妙薬(みょうやく)」と言われ、阿弥陀様の「南無阿弥陀仏」こそが私たちの苦しみの病を根本から治す唯一のお薬ですよ、とおっしゃいます。
お釈迦様のご生涯

〇ご誕生
お釈迦様は約2500年程前、ヒマーラヤの麓にあったカピラヴァストゥを居城とする、釈迦族の王家として誕生しました。
お釈迦様が誕生した直後に東西南北にそれぞれ七歩進み、右手で天を指し、左手で地を指しながら次の言葉を発したと伝えられています。
天上天下唯我独尊 (てんじょうてんげ ゆいがどくそん)
三界皆苦吾当安之 (さんがいかいく ごとうあんし) (『修行本起経』)
前半についてはどこかで聞いたことがある言葉ではないでしょうか?私たちがこの「天上天下唯我独尊」と聞くと真っ先にヤンキーや暴走族が旗に掲げるイメージが浮かびますが、実はこれ、お釈迦様のお言葉なのです。「天上天下唯我独尊」という言葉だけ聞きますと「自分が一番偉い!」というように、傲慢な言葉としてよく誤解されています。大事なのはその後に続く言葉「三界皆苦吾当安之」という言葉です。
「天上天下唯我独尊 三界皆苦吾当安之」というのは「世界で唯一最も尊い生き方がある。それは、迷いの世界で苦しむ人々を安らかにしていくという生き方である(意訳)」というのが正しい解釈です。「自分を差し置いてでも、他者の幸せのために活動していく慈悲の心こそ、この世で最も尊い心なのですよ」と教えてくださるのがこの「誕生偈」と呼ばれる言葉です。
お釈迦様が誕生したと伝えられる4月8日は現在「はなまつり」「灌仏会(かんぶつえ)」というお釈迦様の誕生を祝う行事が営まれています。
・「七歩」の意味
お釈迦様が誕生した直後七歩あゆみを進めた、というのは「迷いの境涯である六道(六界)を超えた存在」という意味があります。
※六道…地獄・餓鬼・畜生・修羅・人・天という6つの迷いの境涯のこと。仏教では人間界だけでなく、天界も迷いの境涯に該当します。
・「甘露の雨」
お釈迦様が誕生した際、天が祝福をし甘露の雨を降らせた、と経典には説かれます。その甘露の雨が降ったという伝説にしたがって「はなまつり」ではお釈迦様の誕生仏に甘茶をかけてお祝いをします。実は誕生の時だけではなく、お悟りを開く時、涅槃に入る時など、お釈迦様の生涯において大事な場面は必ずこの甘露の雨が降ります。肝心な時はいつも祝福の雨。お釈迦様は今でいう「雨男」だったのかもしれませんね。
〇お名前について
現在「お釈迦様」と呼ばれているのは、実は「釈迦族」という部族の名前だったのですね。本当のお名前はパーリ語で「ゴータマ・シッダッタ」といいます。サンスクリット語では「ガウタマ・シッダールタ」。(よく目にする「ゴータマ・シッダールタ」とごちゃまぜに表記しているのは実は誤りですのでご注意を!)お悟りを開いた後は、釈迦族出身の聖者という意味で「釈迦牟尼世尊(しゃかむにせそん)」と呼ばれたから、それを略して「釈尊(しゃくそん)」ともお呼びします。
・コラム…法名(ほうみょう)の「釋(釈)〇〇」の釋ってなあに?
法名を授かる際「釋〇〇」と必ず「釋」の字が上に付きます。これはお釈迦様の「釋(釈)」の字を一字頂き、仏弟子として生きていくことを誓う、という意味があります。
他の宗派では戒名と呼びますが、浄土真宗では法名と呼びます。戒名といったときには仏弟子として出家をして戒律を保ちながら修行をしていくための名前に対し、法名は阿弥陀仏の本願を聞き、南無阿弥陀仏を中心に生きていくことを誓う際に授かる名前です。そう、実は法名とは亡くなってから授かる名前ではなく、本来は生前に授かるお名前。その名前も自分で申請して決めることができます。仏教を聞き、感動する言葉に出会えたならば、その言葉を法名にすることもできますよ!使えない言葉があるなど、制限はありますが、興味がある方は住職に相談してみてください!
〇王族としての生活
王族としてお生まれになったお釈迦様は、王宮の中で何不自由のない生活を送っていました。16歳の時にヤショーダラ妃と結婚をし、ラーフラという子を授かりました。結婚をして、家族に恵まれ、誰もが羨むような生活をしていましたが、お釈迦様はこの頃から思索にふけり、深く人生の問題に悩むようになります。出家するきっかけとなったエピソードをいくつかご紹介します。
・樹下の静観(じゅげのせいかん)
ある日、お釈迦様がまだ少年だった頃、ある木の木陰で休憩しながら、農夫が畑を耕しているのをぼんやりと眺めていました。すると、農夫が耕した土から一匹の虫が掘り起こされ、それを見ていた小鳥が虫をくわえて飛び立ちますが、さらにそれを狙っていた大きな鳥が、その小鳥をとらえて飛び去って行きました。それは一瞬の出来事でした。このような弱肉強食の光景を目の当たりにしたお釈迦様はひどく悲しみました。
「生きるというのはなんて残酷なんだろう。私も生きるためにたくさんの命を奪って生きている。私もいつかあの虫や鳥のように、突然全てを失うことになるのだろうか。それならば今生きている意味は何なのだろうか。」
お釈迦様は一人木の下で思い悩み、長時間静かに瞑想されたとのことです。少年の当時からこの世の苦しみに対して、真剣に向き合っていかれました。
・四門出游(しもんしゅつゆう)
ある日、お釈迦様は従者を連れてお城の外へ出掛けました。城の東西南北にはそれぞれ門があり、お釈迦様はまず東の門から外に出ました。そして、門を出たところでお釈迦様は老人と出会います。
お釈迦様 「従者よ、この者は髭や体が他の者と異なる。この者はどうしたのか?」
従者 「彼は老人です」
お釈迦様 「私もいつかあの老人のようになるのか?」
従者 「そうです。人は誰もが老いていくものです」
従者からそう聞くと、自分の若さが永遠に続くものではなく、この身はやがて老い衰えていくものであることを自覚したお釈迦様は、ひどく気持ちを落としてしまいました。
そのまま出掛けるような気分でいられなくなったお釈迦様は踵を返して門内に戻ると、次に南の門から外へと出ます。するとそこには病に苦しむ人がいました。辛そうに臥せる病人に視線を向けるお釈迦様に、従者はまた告げます。「人は誰もが病に罹るものです」。
今健康に快適に生きているこの肉体も、いずれ病に冒されて苦しむ時が来る。自分もまたいずれ病に侵されること事実を知ったお釈迦様は、またしてもショックを受けて城へと戻るのでした。
次にお釈迦様は西の門から外へ出ることを試みるのですが、そこで出会ったのは死者を送る葬列。沈痛な面持ちで歩く人々と、もはや起き上がることのない死者の姿がそこにはありました。
人間は死に、葬られて骨になることを免れない。生まれた者は必ず死ぬのだという理を突きつけられたお釈迦様は、自分もまた死を避けられない存在であることに恐怖し、またしても城へと戻るのでした。
最後にお釈迦様はお城の北の門から外に出かけます。最後に出会ったのは出家修行者。お釈迦様は従者に尋ねます。
お釈迦様 「従者よ。彼の頭や着ている服は他の者と異なる。この者はどういった者だ?」
従者 「彼は出家者です」
お釈迦様 「出家者とはどういう者なんだ?」
従者 「出家者とは、良い行いを実践することによって苦しみからの解放を目指す者たちのことです」
その出家者の言葉を聞いたお釈迦様はすぐさま決意し、従者に言いました。
お釈迦様 「従者よ。今すぐ車を引き返してくれ。私は今から髪と髭を剃り、袈裟をまとって出家しようと思う」
そしてお釈迦様は29歳の夜半に王宮を抜け出し、出家をされました。
〇苦行と挫折
出家をされたお釈迦様は、いろいろな師を訪ねて回りましたが、どれも悟りを得られる道ではないとして、6年の間、苦行を積みました。絶食などをして難行苦行を行い、座ろうとすれば後ろへ倒れ、立とうとすれば前に倒れるほど厳しい修行を行いました。しかし、一向に人生の苦を根本的に取り除く糸口が見つからないまま時が過ぎ、苦行のみでは悟りを得ることが出来ないと理解し、やがて難行苦行の道を捨てることとなりました。
〇お悟りを開く
お釈迦様は6年続けた苦行を中断し、やっとの思いで近くのネーランジャー川という川で、やつれやせ細った身体を清めました。川から上がったものの、息も絶え絶えであったお釈迦様は、たまたま通りかかった娘によって助けられます。その娘はスジャータという娘で、手には森の神に捧げるための乳糜(牛乳粥)を持っていました。お釈迦様はその乳粥の布施を受け、それによって命を救われたといいます。
心身ともに回復したお釈迦様は心を落ち着かせて、近隣のガーヤ村にある森の大きな菩提樹の下で観想に入りました。そして49日目の12月8日に、ついにお悟りを開きました。
お釈迦様がお悟りを開かれたことを、仏教では「成道(じょうどう)」といい、古来よりこの日に「成道会(じょうどうえ)」という法要を厳修しています。悟りを開いた場所であるガヤー村は、お釈迦様の悟った場所という意味の「ブッダガヤ」と呼ばれ、今でも仏教の聖地としてたくさんの仏教徒が訪れています。
・中道(ちゅうどう)の教え
お釈迦様は王族として豊かな環境に恵まれ「楽」に満ちた生活を送り、やがてそれから出家すると、断食などの厳しく「苦」しい修行に6年間励みます。しかしそれらの苦行を捨てたあと、瞑想のうちに悟りを開きました。「楽でも無く、苦でも無い」自分にあった適切な「中道」こそが正しき道であることに気付かれたのです。
この「中道」の教えを伝える一つの逸話があります。
仏弟子の一人にシュローナという方がいました。シュローナという人は、お金持ちの家に生まれました。子供のころから体が弱く、家族から過保護に育てられます。生活の世話は全部召使がやってくれます。用事があって外に出かける時には籠に乗せてもらい、自分で歩くということはほとんどしませんでした。そんなシュローナという人が青年になり、お釈迦様の弟子になりました。しかしお釈迦様や弟子たちは、毎日、托鉢(たくはつ)といって、食べ物をもらうためにあちこち歩き回ります。今まで全く歩いたことのないシュローナは周りの弟子たちについていくだけでも大変です。しかしシュローナは「皆と一緒のことをしなくてはいけない」といって、一生懸命歩きました。もう一歩も歩けないというところまできて「自分にはやっぱり出家の生活は無理かもしれない。もうこのままやっていく自信がない。やっぱりもとの家に帰ろうか」と思ったそうです。そこへお釈迦様がやってきて、シュローナに声を掛けました。
お釈迦様 「あなたは、ビーナーという楽器の名手だったそうだね」
インドにはビーナーというギターのような楽器があったそうです。シュローナはその楽器の名手でした。
シュローナ 「そうです。ビーナーでしたら多少心得がございます」
お釈迦様 「では聞くが、もし弦があまりにも強く張られていた場合、良い音色を奏でるだろうか」
シュローナ 「いえ、強く張りすぎては良い音は出ません」
お釈迦様 「では、弦があまりに緩く張られたならば、良い音色を奏でるだろうか」
シュローナ 「いえ、弱すぎても良い音は出ません」
お釈迦様 「それでは、ビーナーの弦はどれぐらいの強さで張った時に、一番きれいな音をだすのか」
シュローナ 「一本一本弦の太さが違いますので、まちまちでございます。細い弦には細い弦の、太い弦には太い弦の、適切な張りの強さがございます」
その言葉を聞いたお釈迦様はニコッと笑い「中道の教えも同じである」と答えられました。
お釈迦様は「精進を重ねることも大切だが、あまりにも苛烈な修行に身を置いてしまうと、心が高ぶってしまい静まることがない。また、修行をゆるやかなものにしてしまえば、怠惰の心が湧いてきて修行にならない。だからよいだろうか、シュローナ。あなたはこれから平らな精進に身を置きなさい。身と心を平穏に保つことを目標にして精進をしてみなさい」と伝え、シュローナの心を励ましたそうです。その後シュローナは自分に合った適切な修行によって悟りを開くことができました。
このお話から、自分に合った適切な修行によって仏道を歩むことが大切であることがわかります。煩悩を無くすことができず、命尽きるまで欲望や怒りの炎を燃やし続ける私たちは、凡夫(ぼんぶ)と呼ばれる存在です。私たち凡夫にふさわしい仏道こそ、阿弥陀様の他力の教え、浄土真宗のみ教えなのです。
〇初めての説法
悟りを開かれたお釈迦様は、その教えを他の人に伝えるべきかどうかを迷ったといいます。しかし伝道を決意し、サールナートの地で5人の旧友に向かって初めて説法を行いました。これを「初転法輪」といいます。この説法の内容は、四諦(4つの真理)と八正道(8つの実践方法)に関するものであったと伝えられています。※詳しい内容については「仏教とは」のページをご覧ください。
その後もお釈迦様は生涯にわたって伝道の旅を続け、その名声が広まるとともに、多くの信者達ができました。
〇涅槃に入る
80歳になられた時、体調を壊されたお釈迦様は、故郷に向かう途中のクシナガラの地でサーラの林に横たわり、入滅されました。お釈迦様はたくさんの弟子達に囲まれて、クシナガラの地で肉体を捨てて、完全なる涅槃寂静の世界に入ったのでした。紀元前486年(一説には紀元前386年)の2月15日のことであったといいます。
お釈迦様は亡くなる前に、第一の弟子である阿難(アーナンダ)に、次のように伝えました。
「私は老い衰え、齢も80に達した。この身体は古い車のようにやっと動いているようなものだ。そのようなものをあてにしてはならない。アーナンダよ、汝らは、ただみずからを灯明とし、自らをたよりとして、他人をたよりとせず、法(真理・正しい教え)を灯明とし、法をよりどころとして、他をよりどころとすることをせず、修行するものこそ、わが比丘たちの中において最高処にあるものである」と説法しました。これが有名な「自灯明、法灯明」の教えです。わたくし亡きあとは、法という灯火によって照らされた「自ら」を依り所にし、その自らを照らす「法」を依り所とせよという、お釈迦様の言葉です。
お釈迦様が亡くなられた後、弟子たちはお釈迦様を慕い、残された教えと戒律に従って跡を歩もうとし、説かれた法と律とをまとめ上げました。これらが、現在、幾多の時代と国を越えて、膨大な数の経典や律典として伝えられています。
浄土真宗のいろは

〇ご誕生・出家・得度
親鸞聖人は承安(しょうあん)3年(1173)に誕生されました。父親は日野有範(ひのありのり)という人でした。母親は清和源氏の流れをくむ女性であったと言われていますが詳しいことはわかりません。日野家は藤原氏(北家)に属する中流の貴族でした。親鸞聖人の誕生地は京都市伏見区の日野の里であったといわれています。
・9歳で出家・得度
親鸞聖人が9歳の時、叔父に連れられて青蓮院(しょうれんいん)の慈円慈鎮和尚(じえんじちんかしょう)について得度を受け、出家されます。
親鸞聖人が慈円和尚を訪ねた時、すでに夜だったので「今日はもう遅いから、明日の朝になったら改めて得度の式をしよう」と言われました。しかし親鸞聖人は「明日まで待てません」といい次の歌を詠まれたと伝わっています。
明日ありと 思う心の仇桜(あだざくら)
夜半(よわ)に嵐の 吹かぬものかは
この歌の意味は「今美しく咲いている桜も、明日も見ることができるだろうと安心していると、夜半に強い風が吹いて散ってしまうように、今ある私のこの「命も明日には突然失ってしまうかもれない」という意味です。だからこそ「明日」ではなく「今」仏道に入りたいと訴えたのです。その決意を聞いた慈円和尚はその夜、親鸞聖人の得度式を行い、親鸞聖人は9歳にして出家をされました。こうして得度式を受けて出家をされた時から「範宴(はんねん)」と名乗るようになったと伝えられています。
常に全てのものが移り変わりゆくこの世界で、私たちはついつい「明日あり」と無意識に思っているのではないでしょうか。世の無常と同時に「今桜が咲いている」という自らの命の尊さを伝える名歌です。親鸞聖人のこの歌は日野の誕生院の石碑に刻まれています。是非一度足を運び、ご覧になってください。
〇比叡山(ひえいざん)での学問修行
出家をされた親鸞聖人はやがて比叡山に上り、天台宗の学僧としての道を歩むことになります。親鸞聖人は「堂僧」と呼ばれる修行僧であったといわれています。比叡山にある「常行三昧堂(じょうぎょうざんまいどう)」と呼ばれる道場で「常行三昧(じょうぎょうざんまい)」という修行をする僧を「堂僧」と呼ぶ風習があったことから、親鸞聖人も常行三昧の修行をしていたと考えられています。
・常行三昧の修行
常行三昧堂の中心には阿弥陀仏像が安置されています。修行中は戸を締めて真っ暗なお堂内を太い一本のろうそくの明かりだけが照らしていて夜も昼もわからないようにしてあります。修行者は90日間このお堂に籠り、食事の時とトイレに行く時と風呂に入る時以外は、中心にある阿弥陀仏像の周りを右回りに歩き続け、止まることは許されません。口では南無阿弥陀仏と称え、心は常に阿弥陀仏を念じ続けます。昼夜問わず常に歩き続けることから「常行(常に歩き続ける)」と呼ばれるのです。
・比叡山での焦燥の日々
親鸞聖人はこのような厳しい修行を重ね、ひたすらに歩き続け、南無阿弥陀仏と称え続けました。それは煩悩の火を滅し、阿弥陀仏を目の当たりに拝見して浄土に生まれることを確実にするためでした。しかしどんなに学問を積み、体が壊れるくらいに厳しい修行に励んでも、欲望や名利の煩悩は火は消えることなく盛んに燃え続けて止めることができません。
親鸞聖人は真摯に現実を見つめ、人間の心の弱さ、浅ましさに真剣に向き合っていかれたのでしょう。学問を積み、厳しい修行を積むほど、人間の無力さを思い知り、虚しさを感じていかれるのです。比叡山の修行に行き詰まりを感じ、このままでは迷いの世界から離れることができないと感じていた時、法然聖人の噂が耳に届きます。その法然聖人の噂とは「南無阿弥陀仏のお念仏一つで、煩悩を持った凡夫が救われる道を説いている」という噂でした。その法然聖人のもとに行くべきか、このまま比叡山で修行を続けるべきか、親鸞聖人は迷います。そこで親鸞聖人が29歳の時、観音菩薩の化身であるという聖徳太子にまつわる六角堂に行き、100日間の参篭をする決心をされたのでした。それは自分の歩むべき道を聖徳太子に尋ね、原点に返ってこれからの自分の道を決定していくためでありました。
・コラム…「蕎麦喰いの木像」伝説
参篭には二種類あって、一定期間お寺に籠って願をかける「籠りの参篭」と、毎日通ってお参りをする「通いの参篭」とがありますが、親鸞聖人の六角堂参篭は、比叡山の大乗院から毎日通う、通いの参篭であったとも伝えられています。
この大乗院の伝説によると、親鸞聖人は毎日皆と同じように修行をし、同僚が寝静まったのを見計らい、大乗院を抜けだして六角堂に通っていたといいます。そして皆が起きる前にまた大乗院に帰って来ていたというのです。このような生活を長く続けていますと、当然他の僧の知るところとなり「親鸞聖人は夜な夜な京都に遊びに出かけている」と噂が流れます。そこで師匠の慈円和尚が「ことの真偽を確かめねば」と思い、皆が寝静まった頃を見計らって、僧侶全員を起こして集め、信者からもらった蕎麦を振る舞うという一計を案じます。その日も六角堂に参篭していた親鸞聖人は当然ながらその場にいません。しかし、いないはずの親鸞聖人がそこで皆と一緒に蕎麦を食べていたというのです。それで夜な夜な出ていくことは「単なる噂だった」と慈円和尚は納得し、事なきを得たそうです。親鸞聖人はそのようなことを知らずに、次の日の朝、大乗院に帰ってきます。すると、聖人自作の木像の口元に蕎麦がついているではありませんか。つまり、この木像が親鸞聖人を守るために身代わりとなり、親鸞聖人を守ったという伝説です。この木像は「蕎麦喰いの木像」として伝わっています。なお、大乗院以外に、三十三間堂の東側にある法住寺というお寺にも「親鸞蕎麦喰い像」として祀られています。
〇六角堂の夢告(むこく)
親鸞聖人が六角堂に参篭して95日目に及んだ明け方。聖徳太子の本地(菩薩が化身として現れる仮の姿に対して、本来の菩薩)である観音菩薩が夢の中に現れたのです。その夢の中で観音菩薩は次の言葉をお告げになったと伝えられています。
行者宿報設女犯(ぎょうじゃしゅくほうせつにょぼん)
我成玉女身被犯(がじょうぎょくにょしんぴしんぴぼん)
一生之間能荘厳(いっしょうしけんのうしょうごん)
臨終引導生極楽(りんじゅういんどうしょうごくらく)
この言葉を意訳すると「たとえあなたが戒律を破り、女性と結婚することになったとしても、わたくし(観音菩薩)が麗しい女性となってあなたの妻となりましょう。そしてあなたの一生を仏道として美しく荘厳し、命の終わりには極楽浄土へ導いていきましょう」という意味です。
親鸞聖人にとってこの夢のお告げは、やむを得ず戒律を破り、妻帯して一般の人のように家族を持って生活をすることになったとしても極楽へ生まれることのできる道があるということ、しかもそれは阿弥陀様に常に付き従い、隣に控える菩薩である観音菩薩が認められた真の仏道であるということを暗示していました。
その道こそ法然聖人が説かれる「戒律を守る守らないに関わらず、ただ本願を信じ念仏を申せば極楽に生まれる」という南無阿弥陀仏のお念仏の道に通じるのではないか。このように観音菩薩の夢のお告げに後押しをされ、親鸞聖人は比叡山を下りて法然聖人を尋ねていかれたのです。建仁元年(1201)4月5日の暁のことでした。
・コラム…親鸞聖人ご夫婦が、生涯知ることのなかった、お互いの秘密。
親鸞聖人は法然聖人の弟子になると、恵信尼と呼ばれる女性と家庭を築き、家庭の中にありながら仏道を歩む、念仏者として人生を送ります。先の観音菩薩のお告げを聞いている親鸞聖人は、妻の恵信尼のことを、お浄土に導いてくださる「観音菩薩の化身」として心から信じていました。しかし、このことは妻の恵信尼には知らせていません。
親鸞聖人ご夫妻が常陸国(ひたちのくに、現在の茨城県)に住んでいた時、恵信尼はある晩、不思議な夢を見ます。それは次のような夢でした。
気が付くと、どこかのお堂の宵祭りにいました。松明があたりを明るく照らし、音楽が奏でられています。お堂の前には鳥居のようなものがあり、その横木には2体の絵像が描かれた掛け軸がかけてありました。1体は光がまぶしく、お顔が見えませんでしたが、仏の頭光のように輝いていました。もう1体はまさしく仏様のお顔でした。不思議に思って近くの人に「これは何という仏様ですか?」と尋ねたところ「あの光り輝くお方は、法然聖人です。大勢至菩薩(だいせいしぼさつ)であらせられます」というのでした。「それではもう1体のご絵像は?」と尋ねると「あれは観音菩薩です。あなたの夫、親鸞聖人です」と言われ、驚いてそこで目が覚めました。
恵信尼が目を覚ました時、この夢の法然聖人に関する部分だけを夫の親鸞聖人に話したところ「それは実夢である。法然聖人は、阿弥陀仏の智慧の徳をあらわす大勢至菩薩の化身であるといわれているし、智慧は光で表されるから、道理にかなっている」とおっしゃられました。「親鸞聖人が観音菩薩(阿弥陀仏の慈悲の象徴)」であったということは本人には伝えませんでしたが、それ以降、夫のことを「観音菩薩の化身」だと信じてお仕えしていったと、娘への手紙の中で告白しています。
つまり、親鸞聖人は観音菩薩の夢のお告げによって「妻の恵信尼のことを観音菩薩の化身」だと信じ、恵信尼もまた夢のお告げによって「夫の親鸞聖人のことを観音菩薩の化身」だと信じていたのです。お互いがお互いのことを「菩薩の化身」と信じ、そのことはお互いに明かさず、ついにはお二人の生涯の内にはその秘密を知ることはありませんでした。皮肉なことに、二人のそれぞれの秘密を知ることができるのは、お二人の書物を見ることのできる、今に生きる私たちだけなのです。
〇法然聖人との出会い
法然聖人は親鸞聖人に対し「阿弥陀様という仏さまは、平等の慈悲をもって善人も悪人もわけへだてなく救うために、誰でも歩める仏道として南無阿弥陀仏のお念仏をお浄土に生まれるための行として選び取られた。阿弥陀様の「お願いだから南無阿弥陀仏のお念仏を称え、浄土に生まれ来たれ」という本願を疑いなく受け入れて念仏するものは、どんなに重い煩悩を抱えた人であってもお浄土に生まれさせていただき、仏とさせていただくのである」と説かれたのでした。それは今まで親鸞聖人が学んできた、悪を慎み、善を積み、自らの心を浄化しなければいけないという自力の教えとは全く異なった教えでした。この平等の教えに触れたとき、親鸞聖人はしびれるような感動に包まれたのです。こうして親鸞聖人は「法然聖人の行かれる所ならば、どこまでもついていこう。それがたとえ地獄であったとしても、決して後悔はしない。なぜならば、他のいずれの修行にも耐えられない愚か者の私には、どちらにせよ地獄にしか行き場がないのだから」と、南無阿弥陀仏のお念仏の道に入り、阿弥陀様の本願を中心に生きていく、新たな人生を歩み始めるのです。
この時、法然聖人は親鸞聖人に「綽空(しゃっくう)」という法名を授けます。こうして親鸞聖人29歳の時、南無阿弥陀仏のみ教えは親鸞聖人の90年という生涯を決定づけていくのでした。
〇法然聖人と同じ信心?違う信心?~信心一異の諍論(しんじんいちいのじょうろん)~
親鸞聖人が33歳の時、法然聖の主著である『選択本願念仏集(せんじゃくほんがんねんぶつしゅう)』の相伝を許されます。この本は、その教えを正しく理解できる者にだけひそかに伝授されるものでした。入門してわずか4年ほどしか経っていない親鸞聖人に伝授されたのは、それほどに親鸞聖人が認められていた証拠でしょう。この日、それまで名乗っていた「綽空」の名を改めて「善信(ぜんしん)」と名乗ることを法然聖人に認められます。
親鸞聖人が34歳の頃、同門の兄弟子たちと論争が起こります。ある日、親鸞聖人が「この善信の信心も、法然聖人の信心も、全く同じ信心である」といわれたところ、同門の兄弟子たちが「師匠である法然聖人と、弟子になったばかりのお前の新人が全く同じなんて、よくそんなことが言えたな!そんなことはもってのほかだ!」と反対したのです。しかし親鸞聖人は「師匠の法然聖人がお持ちになっているような深い智慧や学識と同じであると言ったならば、それは確かに絶対にありえない話ですが、阿弥陀様の本願を疑いなく信ずる信心は、全く異なることはありません」と返答します。けれどもなおも「智慧や学識が違えば、信心にも浅い深いの違いが出てくるはずだ!」と、おさまりがつかなくなり、最終的には法然聖人を前にして、どちらの言い分が正しいか、その是非を決めてもらうことになりました。
法然聖人が事の詳細を聞くと、親鸞聖人と弟子たちを前に「この法然の信心も、阿弥陀様からいただいた信心です。善信(親鸞聖人)の信心も、また阿弥陀様からたまわった信心です。それゆえ、全く同じ信心です。もし異なった信心をもっていたとするならば、この法然がまいらせていただくであろう同じお浄土へは、うまれることはできないでしょう」とおっしゃられたのでした。
阿弥陀様からいただく信心だからこそ、同じ信心であり、心をすまして称えるお念仏も、散り乱れて汚れた心で称えるお念仏も、賢いものが称えるお念仏も、愚か者が称えるお念仏も、全く同じ功徳を持つお念仏なのです。同じ阿弥陀様から、同じ本願の言葉を疑いなく聞き受ける人の心には、同じく仏の心が宿っているのです。今この時代を生きる私たちも、同じ阿弥陀様の本願を疑いなく聞き受けているのであれば、法然聖人、親鸞聖人とまったく同じ信心を頂いているという事になるのでしょう。
〇弾圧と流刑
法然聖人の名声が上がり、南無阿弥陀仏のお念仏の仏道に帰依する信者が多くなるにつれて、聖人とその一門のお念仏の教えに対する、他宗派からの反感は次第に強まり、念仏弾圧に向けての動きがみられるようになりました。
元久(げんきゅう)元年(1204)の10月、ついに比叡山の大衆が一斉に蜂起し、天台の座主(ざす)に念仏の全面禁止を訴え出ました。さらに元久2年(1205)10月には興福寺から「法然聖人が説かれているお念仏の教えは過ちである」という内容の「興福寺奏状(こうふくじそうじょう)」が朝廷に送られることになったのです。「医者が病の重いものを真っ先に救っていくように、煩悩の深い愚か者こそ救いの対象である」という仏の目線に立った平等の教えは、当時の仏教界からはなかなか受け入れられなかった思想であったのでしょう。
そしてついに承元(じょうげん)元年(1207)2月に法然門下への死罪、流刑が始まり、法然聖人は土佐の国へ、親鸞聖人は越後の国(現在の新潟県直江津市)に流刑となりました。
〇僧侶でもなく、世俗でもなく~非僧非俗(ひそうひぞく)としての生活~
流刑に処された親鸞聖人は、僧籍も剥奪されてしまいます。この時、親鸞聖人はご自身のことを「今の私は僧侶でもなく、かといって世俗の人でもない。このような私だからこそ「愚か者」を意味する「愚禿」という言葉を姓として「愚禿釈親鸞(ぐとくしゃくしんらん)」と名乗って生きていこう」とおっしゃられました。
「僧侶ではない」とおっしゃられたのは、単に僧籍を奪われたという意味ではなく自身の心を省みて「欲望の海に沈み、名声に執着してしまって煩悩の心を離れることができず、さらに阿弥陀様のお浄土に生まれることを喜べないこの私は、僧侶を名乗る資格がない」という仏法に照らして自らを恥じる心から出てきた言葉でしょう。親鸞聖人が結婚されたのは、ただ煩悩に負けて出家の道から逃げ出したというものではなかったというべきです。むしろ苦悩の者を救うという阿弥陀様の本願のお救いを普通の人々と同じ生活の中で確かめようとされたからです。そこに世俗を超える仏道の意味を見出されたのでした。
「世俗の人でもない」というのは、世俗の生活をしながらも阿弥陀様の本願を聞き、仏道を歩む念仏者としての自覚があったからでしょう。煩悩に惑わされながらも、阿弥陀様のみ教えに心の手綱を握っていただき、自分自身に騙されないよう、常に仏様を心の中心に据えて生きていくということが念仏者にとって大切な心がけでした。そこに念仏に常に育てられ続けていく「世俗ではない」生き方が恵まれていくのです。
このような親鸞聖人の「非僧非俗」の生き方は「仏教を世俗化させた」という方もいらっしゃいます。しかしそれは大きな間違いであり、阿弥陀様の本願のみ教えは「世俗を仏道に高めていく」教えであるというべきでしょう。
〇関東での教化
建暦元年(1211年)11月17日、法然一門の流刑が解かれました。法然上人は京都に戻られてすぐに、かねてからの病によって東山大谷でお亡くなりになりました。
親鸞聖人は越後から常陸国(ひたちのくに、現在の茨城県)に移り、以降20年の間、関東に留まって教えを広められました。その間に『顕浄土真実教行証文類』(教行信証)の執筆を始められたと伝えられています。執筆を始めた頃、京都では再び専修念仏の弾圧が行われていました。法然上人のお墓は破却され、『選択本願念仏集』の板木の消却がされ、弾圧によって専修念仏信仰の芽が次々とつみ取られていくのでした。親鸞聖人は関東にいて処罰を逃れましたが、その悲しい知らせを聞くにつれ、『教行証文類』執筆の意欲は一層増大したことでありましょう。
親鸞聖人は、62歳頃に、関東から京都に帰られました。京都から帰られてからは『教行証文類』を完成させるとともに、『和讃』をはじめ多くの書物を著し、また関東から訪ねてくる門弟たちに浄土の法門を教授し、あるいは書簡を送って遠国の門弟達を指導していかれました。しかし、関東を去った後、東国教団のなかには念仏を曲解する者もあらわれました。煩悩不足の身であるからといって「悪いことを好きなだけしても良い」というような教えの受け止め方をするものが出はじめたのでした。そこで聖人は息男の善鸞を東国につかわしてその間違いを静めようと試みましたが、親鸞聖人の説くところと違った教えを説いて、さらに混乱をきたす事件を起こしてしまいました。それを知った聖人は、父と子の縁を絶つ以外に事態を収拾する道のないことをさとり、善鸞を義絶し、親子の縁を絶ってしまいました。このとき親鸞聖人84歳でした。
〇ご往生
このような事件が起こったこともあり、親鸞聖人は80歳を過ぎてもなお精力的に著述を進め、特に多くの書状をしたためて、関東の門弟たちの信心と生活の指導に努められました。親鸞聖人の著述は『教行信証』をはじめ十数部にのぼります。
そして90歳となられた弘長2年(1262年)11月28日、三条富小路にあった弟・尋有の善法坊で、末娘の覚信尼さまに見守られながら、往生をされました。
浄土真宗本願寺派では親鸞聖人が往生された1月16日(旧暦の11月28日)に、毎年本願寺にて「御正忌報恩講法要」が営まれます。
・愚者(ぐしゃ)になりて往生(おうじょう)す
親鸞聖人が88歳の時、36歳を最後にお会いしていない法然聖人のことを思い出しながら、次のようなお言葉を記されています。
「浄土宗の人は愚者になりて往生す」
愚者とは、字のごとく「おろか者」という意味です。阿弥陀様の教えに導かれながら生きている念仏者は、仏様の教えに照らされてあらわになる煩悩まみれの「おろか者の私」に気づかされ、自身の煩悩を認めながら、自分の弱さを受け入れて生きていく生き方を知らされます。このことを法然聖人は
「聖道門(しょうどうもん)の修行は 智慧(ちえ)をきわめて生死(しょうじ)を離る
浄土門(じょうどもん)の修行は 愚痴(ぐち)にかえりて極楽にうまる」
とおっしゃっていました。聖道門とは自力の仏道のことですが、自力の教えでは自らのさとりの智慧を磨いて煩悩を滅却し、迷いの世界を離れようとすることが修行の目的です。それに対して阿弥陀様のお浄土に生まれようと目指す他力の教えでは、自らが煩悩まみれの愚か者であると気づかされ、本来の弱い自分を受け入れていくことこそが修行になるのでしょう。
煩悩をもつ自分の姿を恥じながらも、阿弥陀様のお救いを喜びながら生きていく。仏の光と煩悩の闇が共存していくような人生を歩んでいくのが念仏者の生き方なのです。90年にもわたる親鸞聖人の「非僧非俗」のご生涯は、まさに「愚者になりて往生す」る道場であったのでしょう。